がん検診について
「検診」は症状のない健康な人が対象です

がんによる早すぎる死を防ぐために、知って欲しい事実があります。
「がん情報サービス」
は国立がん研究センターがん対策情報センターのウェブサイトです。がんについて、がんの向き合い方、診断・治療方法、緩和ケアについて、病院検索など、さまざまな情報を調べることができる、がん情報の入口です。
「検診」と「診療」の違いについて
「検診」がんのリスクの低い沢山の健康な人々のなかから、「検診」というふるいにかけて、がんの疑いのある人を分けるためのシステム。ふるい分けられたがん疑いの人にのみに精密検査が行われる。
「診療」自覚症状があり、受診している人は、がんの可能性が高く、ふるい分けのための検査では不十分。診断を目的として最初から精密検査を用いる。
検査方法について
最先端の検査法であれば、効果があるわけではありません。どんなにがんを見つける力が強くても、効果があるとは限りません。
「死亡リスクが下がること」が科学的に証明された検診でなければ効果はありません。
日本の5つの「がん検診」
これらの方法は、有効性(死亡を防ぐ効果)があるということが科学的に証明されている検診です。また、検診のメリット・デメリットを検討して、対象となる年齢や受診間隔が定められています。
| 対象臓器 | 検診方法 | 対象者 | 受診間隔 |
| 胃 |
問診に加え、胃部エックス線または 胃内視鏡検査のいずれか |
40歳以上 50歳以上 |
1年に1回 2年に1回 |
| 肺 | 質問(問診)、胸部エックス線検査および喀痰細胞診(原則50歳以上で喫煙指数が600以上の方のみ。) | 40歳以上 | 1年に1回 |
| 大腸 | 問診および便潜血検査 | 40歳以上 | 1年に1回 |
| 乳房 | 問診および乳房エックス線検査(マンモグラフィ) | 40歳以上 | 2年に1回 |
| 大腸 | 問診および便潜血検査 | 40歳以上 | 1年に1回 |
検診のメリット・デメリット がん検診の流れ
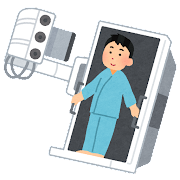
がん検診は、最初のスクリーニング検査と呼ばれる検査だけでは意味がありません。「異常あり」と判断された場合には、必ず精密検査や、診断・治療を受けることが必要です。
「異常あり」となった方から、がんが見つかる割合は、がん検診によって異なりますが、約1.5%~4.5%です。また、がん検診で見つかるがんの多くが、治癒可能な「早期がん」です。
また、「異常なし」となった場合でも、次回の検診を受診することが重要です。
検診のメリット
- がんにより亡くなることを防げます。
- 前病変を治療することで、がんになることを防げます。
(例)子宮頸がん、大腸がん
検診のデメリット
- 検診や精密検査に伴う偶発症
放射線被ばくや、出血、腸管穿孔
- 偽陽性(誤って、がん疑いありと判定されること)
不必要な精密検査
検査結果が分かるまで不安
- 偽陰性(誤って、がん疑いなしと判定されること)
治療の遅れ
- 過剰診断
死亡につながらないがん、つまり実は見つける必要もないがんを見つけて治療してしまう可能性(そのようながんと治療すべきがんの区別はできません)
集団検診と個別検診
集団検診
保健センターにて実施日に検診バスに乗り検診をうけていただきます。
お近くでお安くうけていただけます。
申込日より、お電話かwebから申し込んでください。
詳細は保健事業予定表を確認してください。
個別検診
指定の医療機関でご自身で予約をとり検診を受けていただきます。
実施期間 5月1日~1月31日
保健センターで問診票を交付しますので、先に保健センターへお電話か、webから申し込んでください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒636-0053
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目2番9号
電話:0745-56-6006
ファックス:0745-56-5353








更新日:2025年04月01日